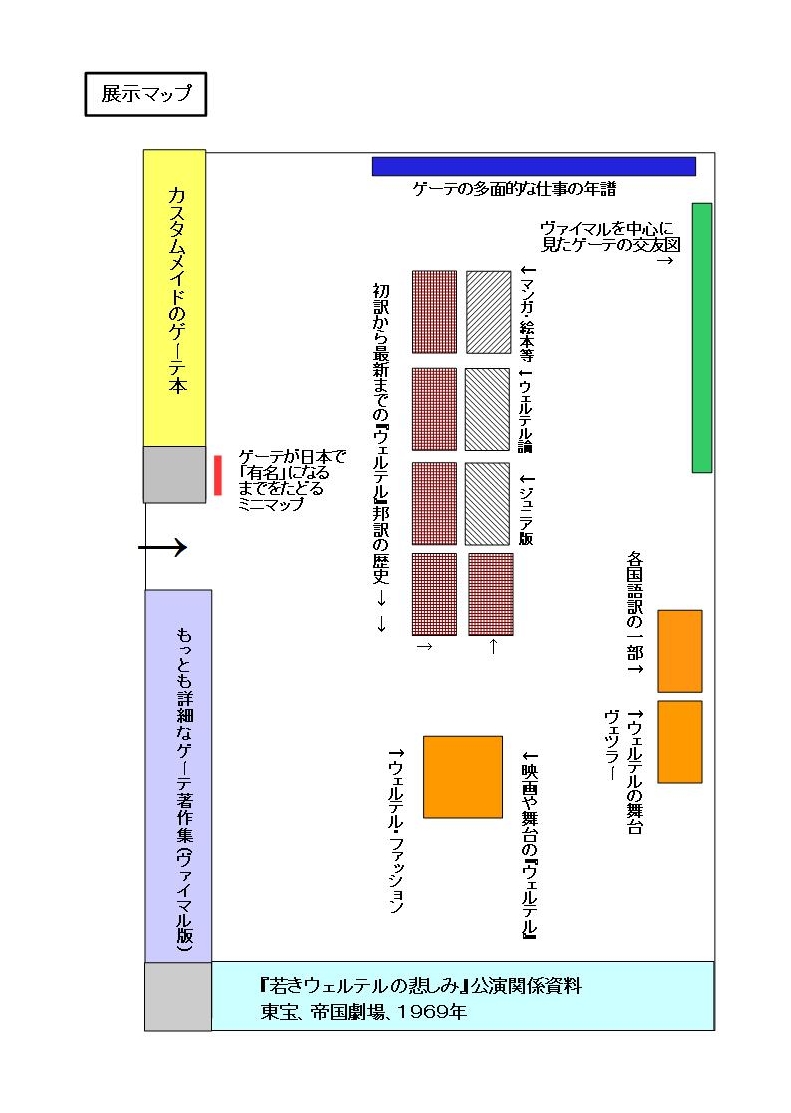ゲ―テの『若きウェルテルの悩み』は、ゲーテ自身の恋愛体験にもとづく感傷的なラブストーリーと受け取られる面がありますが、書簡というスタイルからして、すでにゲーテは主人公ウェルテルに距離を取っています。
カール・W・イェルーザレムという青年をモデルにしたことをゲーテは自伝『詩と真実』のなかで言っていますが、ゲーテがこの青年に関心を持ったのは、当時の青年たちのように、中世の騎士時代に憧れたり、舞踏会に入れ込んだりは全くせず、ひたすら「自分と自分の信念 (Gesinnungen)に生きていた」からだったようです。
映画や小説で「情熱」や「熱愛」に慣れてしまったわたしたちからすると、ウェルテル程度の「信念」は普通じゃないかと思われるかもしれませんが、格式や因習にこりかたまったあの時代に「自分の信念に生きる」ということは全然「普通」ではなかったのでした。
ゲーテほど「自分を生きた」ひとはいないかのようにみえても、宮廷政治の世界を生き抜いたひとです。ウェルテルのような「過激」さを持ちながら、それを隠す「貴族」的なしたたかさもそなえていたのがゲーテでした。
発行後すぐに発禁のスキャンダルまで起こしたこの小説は、貴族のあいだではその「感傷的」な側面が、「市民」(のちにフランス革命の主体になる)のあいだでは、その「一途な過激さ」が共感を呼びました。
『ウェルテル』は、あい対立する階級のあいだで受けたのです。メロドラマとして、そして、世に逆らう主人公の小説として。